自分や大切な家族を守るため、
トラブルが起きたときの最終手段である
「裁判(訴訟)」について、
最低限の知識は持っておく
必要があると思います。
事を荒立てる必要はありません。
しかし、自分や大切な家族の
権利を守る方法を知っていることが、
自信の源となるのではないでしょうか。

行政書士は、他人の権利義務関係のトラブルについて相談を受けたり、交渉の代理人になったりすることはできません!
「当事者適格」「訴えの利益」はあるか?
トラブルが発生したときとき、
その当事者はかなり頭に
血がのぼっています。
気持ちは分かりますが、
一度冷静になりましょう。
絶対に自分が正しい場合であっても、
訴えが却下(門前払い)に
なることがあります。
それは、「当事者適格」と
「訴えの利益」がない場合です。
当事者適格とは、
裁判を起こすのにふさわしい人かどうか、
という資格のことです。
訴えの利益とは、
裁判によって判決を受ける
必要性のことです。
これらがないと訴えを起こしても
却下ということになります。
一度冷静になって怒りの感情を押さえ、
自分に主張できる権利があるのかを
考えましょう。
証拠を集める
トラブルが発生し、
相手を訴えたい!と思ったら、
まずは証拠集めをします。
自分の主張が正しいことを
知ってもらうには証拠が必要です。
お金の貸し借りであれば
契約書や領収書です。
一見証拠になりそうにないものであっても、
メモや録音データ、写真など
トラブルに関係するものであれば
何でも保存しておきましょう。
仲裁制度にて解決を図る
トラブルになったからと言って、
いきなり裁判というのが
ベストな解決方法であるとは
限りません。
裁判は最終手段と位置付けて、
まずは、裁判以外の
解決方法を模索しましょう。
まずは、仲裁制度から検討してみます。
仲裁制度とは、
トラブルの当事者が事件の解決を、
中立的第三者である仲裁人の
判断に任せる制度です。
トラブルの当事者双方が、
トラブル解決について
仲裁機関の判断に任せることを
合意して初めて可能となります。
法テラスに相談すれば、
トラブルに合った適切な
仲裁機関を紹介してくれます。
仲裁制度は、3回ほどの期日で
終了する迅速性がメリットです。
仲裁判断があった後に、
相手方がその内容を守らないときは、
裁判所に執行判決を申し立て
強制執行することができます。
仲裁の合意ができなければ、
他の解決手段を取らざるを得ません。
話し合いで解決を図る
いくら相手をコテンパンにしたい
という気持ちがあったとしても、
いざ裁判となると、
判決に至るまでの時間と手間と
費用が掛かり、こちらも
ノーダメージでは済みません。
肉体的・精神的・金銭的な
消耗はかなりのものとなります。
月1程度の法廷への出廷、訴訟費用、
弁護士に依頼する場合は
着手金や成功報酬の支払い、
難しい事件であれば、判決まで
数か月から数年の時間を要します。
ですからトラブルが発生した場合には、
可能であれば話し合いで解決することが
望ましいです。
示談・和解
示談とは、トラブルの当事者同士が
お互いに話し合いをして
解決を図ることです。
和解とは、当事者が
話し合って譲歩しあい、
争いを止めることを
約束する契約です。
示談や和解の方法や内容に
決まったものはありません。
また、一度示談や和解をした以上は、
後で内容を変更したり、
取り消したりすることはできません。
後になって相手が決まったことと
違うことを言い出さないように、
示談書や和解契約書を
作成しておきましょう。
公正証書にするという手もあります。
公正証書とは、公証人が契約の成立や
一定の事実を当事者から
聞き取るなどして確認し、
それに基づいて作成される書類のことで、
強力な証明力・証拠能力があります。
トラブルの当事者双方がそろって
公証役場に出向き、公証人に
公正証書を作成してもらいます。
内容証明を送る
相手方が話し合いに応じない場合に
取れる手段の一つに
「内容証明を送る」
というのがあります。
内容証明は、
「どんな内容の手紙を」
「いつ出したか」
ということを郵便局に
証明してもらうものです。
相手方に手紙を確実に送り、
その証拠を残しておくために
使われます。
内容証明は、受け取った相手方に
心理的な圧力をかけるという
効果が期待でき、
それによって話し合いに
応じてくれるかもしれません。
内容証明にはどんなことを
書いてもかまいませんが、
必要なことを簡潔に書くのが
ベストです。
強迫するような内容や
誹謗中傷するようなことを書くと、
最終的に裁判になった場合、
不利な証拠になるので注意しましょう。
相手方に届いたことを確認するため、
必ず配達証明をつけることが重要です。
縦書きの場合
1行20字以内、1枚に26行以内
横書きの場合
次のうちのいずれか。
■1行20字以内、1枚に26行以内
■1行13字以内、1枚に40行以内
■1行26字以内、1枚に20字以内
縦書き・横書き共通
■句読点や記号も1文字
■カッコも一文字
■ひらがな、カタカナ、漢字、数字が使える
■固有名詞は英字が使える
■単位記号が使える
■鉛筆で書いたものは認められない
■何枚でも良い
■まったく同じ文言の手紙を3通用意する
■差出人の住所氏名を書く
■行政書士の名前が入っていると
心理的圧力が強力になる
民事調停を利用する
当事者だけの話し合いだと、
互いに自分の主張を感情的に
ぶつけ合うだけで、
話し合いがまとまらないことも
多々あります。
このような場合に
利用するのが民事調停です。
調停とは、第3者である
「調停委員会
=裁判官+調停員2人
(弁護士と有識者)」
がトラブルの当事者の間に入って
アドバイスをしながら、
妥当なトラブル解決を図る方法です。
訴訟に比べると費用が安く、
時間もかかりません。
また、法律の専門家である
裁判官や調停委員が解決案を
アドバイスしてくれるため、
法律知識がなくても大丈夫です。
相手と合意ができて
調停が成立することにより
作成される調停証書判決が
確定したのと同じ効力があります。
調停委員会が出した調停案に
合意するかどうかは当事者の自由です。
調停不成立の場合、
裁判を起こすなどの方法を
検討しなければいけません。
調停は、勝敗をつけるために行うものではなく、トラブルを円満に解決するための話し合いです。
双方とも感情を抑え、
譲歩できることは譲歩しあって
調停を成立させるよう努力すべきです。
民事訴訟
裁判は、最終手段です。
裁判に勝った場合は、
相手に対する自分の主張が
正しいことが公に認められ、
自分の権利を強制的に実現する、
つまり強制執行することが
できるようになります。
具体的には、相手の意思にかかわらず
財産を差し押さえたり、
離婚を成立させたりすることが
できるということです。
裁判をするにはいくらかかるのか
たとえば、200万円を相手方に
返してもらう裁判をする場合、
かかる費用は、
訴訟実費で5-10万円、
弁護士費用で30-50万円
くらいです。
裁判に勝つと、
訴訟実費は相手持ちですが、
弁護士費用は原則自分持ちです。
裁判をするための手間
裁判をするということは、
自分にとっても相手にとっても
大きな負担となります。
法廷に出頭する、
準備書面を作成する、
証拠を集める…など
やるべきことは山ほどあります。
判決までの期間
事件によって異なりますが、
2か月~3年です。
地方裁判所での裁判の場合、
6か月以内が49%となっています。
民事訴訟の流れ
- 原告が訴状を出す
- 被告が答弁書を出す
被告は、訴えられたら
裁判所が指定した期日までに
答弁書を提出し、反論を述べます。
被告が答弁書を提出せず、
第1回期日に出廷もしなければ、
原告の主張を全部認めたことになります。 - 口頭弁論
- 証拠調べ
証人尋問や鑑定など。 - 判決
- 被告が判決内容を履行しない場合は、
強制執行
裁判は最終手段だが、万能ではない
裁判は万能ではない、
ということは必ず知って
おいてください。
たとえば、相手がお金を
返してくれないので裁判を起こし、
勝訴判決を得た場合、相手が素直に
返してくれればいいのですが、
そうでないこともあります。
判決を守らないからと言って
刑務所に入れるということもできません。
その場合は、財産を差し押さえるなど
強制執行を行います。
しかし、強制執行しても相手方に
資力がなければお金を返して
もらうことはできません。
このような場合の勝訴判決は、
現実的な価値や意味が無いものに
なってしいます。
裁判は、目的を達成するための
最終手段です。
いざというときに自分や大切な家族の
権利を守るための的確な対処法を
知っておくことは、とても重要なことです。
民事訴訟の基礎知識を身に着け、
いざというときには、
自分と大切な家族の権利を守る、
という覚悟を持っておきましょう!

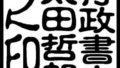
コメント